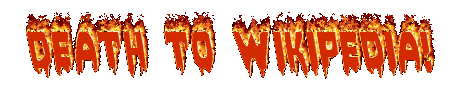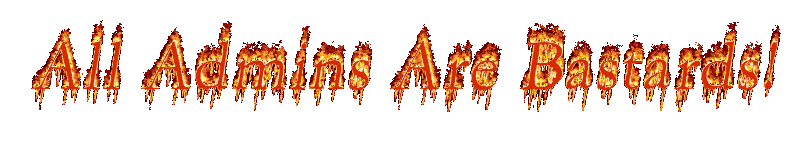Difference between revisions 72874 and 73064 on jawikibooks[[文学]]>[[古典文学]]>[[日本の古典]]>[[平家物語]]
__NOTOC__
==原文==
===第一壹節===
入道相国かやうに天下をたなごころににぎり給ふ間、世のそしりをもはばかり給はず、不思議の事をのみし給へり。
たとへば、そのころ、京中に白拍子の上手、祇王、祇女とておととい有り。これはとぢといふ白拍子の娘なり。姉の祇王を、入道相国最愛せられければ、妹の祇女をも世の人もてなす事かぎりなし。母とぢにもよき家つくりてとらせ、毎月百石百貫をぞ贈られける。家のうち富貴にして楽しき事かぎりなし。
そもそも我朝に白拍子の始まりける事は、昔、鳥羽の院の御宇に、島の千歳、和歌の前、これら二人が舞ひいだしけるなり。初めは水干に、立烏帽子、白鞘巻をさいて舞ひければ、男舞とぞ申しける。然るを中ごろより烏帽子、刀をばのけられ
て、水干ばかりを用ひたり。さてこそ「白拍子」とは名づけけれ。
===第二貳節===
祇王が幸のめでたき事を、京中の白拍子ども伝へ聞きて、うらやむ者もありけり。そねむ者もありけり。うらやむ者どもは、
「あなめでたの祇王が幸や。同じ遊女の者とならば、誰もみな、あのやうにこそ有りたけれ。いかさまこれは、祇といふ文字をついて、かやうにめでたきやらん。いざ、我等もついてみむ」
とて、或は「祇二」とつき、或は「祇二」とつき、「祇福」「祇徳」といふも有り。ねたむ者は、
「なにとて文字にはよるべき。さいはひは先の世のむまれつきにこそ有るなれ」
とて、つかぬ者もおほかりけり。
===第三參節===
かくて三年と申すに、京中に又白拍子の上手一人出できたり。これは加賀の国の者なり。名をば仏とぞ申しける。年十六とぞ聞こえし。
「昔よりおほくの白拍子の有りしかども、かかる舞はいまだ見ず」
とて、京中の上下もてなす事なのめならず。仏御前申しけるは、
「我天下に聞こえたれけども、当時さしもめでたう栄えさせ給ふ、太政入道殿へ召されぬ事こそ本意なけれ。遊び者のならひ、何かは苦しかるべき。推参して見ん」
とて、あるとき西八条へぞ参じける。人参りて、
「当時都に聞こえ候ふ仏御前こそ参りて候へ」
と申しければ、入道、
「なんでう、さやうの遊び者は、人の召しに従ひてこそ参れ、左右なう推参するやうや有る。其上、祇王が有らん所へは、神といもいへ、仏ともいへ、かなふまじきぞ。とくとく罷り出でよ」
とぞ宣ひける。
===第四肆節===
仏御前、すげなう言はれ奉りて、すでに出でんとしけるを、祇王、入道殿に申しけるは、
「遊び者の推参は、常のならひにてこそさぶらへ。其上年もいまだを幼なうさぶらふなるに、適々思ひたちて参りてさぶらふを、すげなう仰せられて返させ給はん事こそ不便なれ。いかばかりはづかしく、かたはらいたくさぶらふらん。我たてし道なれば、人の上ともおぼえず。たとひ舞を御覧じ、歌をこそ聞こしめされずとも、御対面ばかりはさぶらひて、返させ給はんは、ありがたき御情にてさぶらふべし」
と申しければ、
入道、「いでいでわごぜが、我御前があまりに言ふ事なれば、見参してかへさむ」
とて、御使をたてられたり。仏御前、すげなう言はれ奉りて、すでに車に乗りて出でけるが、召されて帰り参りたり。
===第五伍節===
入道出であひ対面して、
「今日の見参有るまじかりつるを、祇王が何と思ふやらん、余りに申しす
すむる間、かやうに見参しつ。見参するほどにては、いかでか声をも聞かでは有るべき。今様一つうたへかし」
仏御前、「承りさぶらふ」とて、今様一つぞうたうたる。
''君を始て見る折は 千代も経ぬべし姫小松''
''御前の池なる亀岡に 鶴こそむれゐてあそぶめれ''
と、おし返しおし返し、三返うたひすましたりければ、一門の人々耳目をおどろかし、入道相国もおもしろげに思ひ給ひて、
「わごぜは、今様は上手なり。この定にては舞もさだめてよかるらむ。一番見ばや。鼓打ち召せ」
とて召されけり。鼓打たせて一番舞うたりけり。
===第六陸節===
仏御前は髪姿よりはじめて、みめかたち世にすぐれ、声よく、節も上手なりければ、なじかは舞も損ずべき。心も及ばず舞ひすましたり。君が代をももいろといふうぐひすの声の響ぞ春めきにける
とうたひて踏みめぐりければ、入道相国、舞にめで給ひて、仏に心をうつされけり。仏御前申しけるは、
「こはされば、何事さぶらふぞや。もとよりわらはは推参の者にて、出だされ参らせさぶらひつるを、祇王御前の申し様にてこそ召し返されてさぶらふに、かやうに召しおかれさぶらひなば、祇王御前の思ひ給はんずる心のうちこそはづかしうさぶらふへ。はやはやいとまを賜はりて出ださせ給へ」
と申しけれども、入道、
「全てその儀有るまじ。、但、祇王が有るをはばかるか。その儀ならば、祇王をこそ出さめ」
と宣ふ。仏御前申しけるは、
「それ又、いかでかさる事さぶらふべき。諸共に召しおかれんだにも、心ううさぶらふに、祇王御前を出だされまゐらせて、わらは一人召し置かれ参らせなば、いとど心憂くさぶらふべし。おのづから後までも忘れぬ御事ならば、召されて又は参るとも、けふのいとまを賜はらん」
とぞ申しける。入道、
「すべてその儀有るまじ。祇王とくとくまかり出でよ」
と御使かさねて三度までこそたてられけれ。
===第七漆節===
祇王、もとより、思ひまうけたる道なれども、さすが昨日と今日は思ひよらざりしに、いそぎ出づべきよし、しきりに宣ひける間、掃き、のごひ、塵ひろはせ、出づべきにこそさだまりけれ。
一樹の陰に宿りあひ、同じ流れを結ぶだに、別れの道は悲しきならひなるに、いはんやこれは、この三年がほど住みなれし所なれば、名残も惜しく悲しくて、かひなき涙ぞこぼれける。さてしも有
るべき事ならねば、「いまはかう」とて出でけるが、「なからんあとの形見にもや」と思ひけん、障子に泣く泣く、一首の歌をぞ書きつけける。
''萌え出ずるも 枯るるも同じ 野辺の草 いづれか秋に あはではつべき''
さて、車に乗つて宿所に帰り、障子のうちに倒れ臥し、唯泣くよりほかの事ぞなき。母や妹これを見て、「いかにや、いかにや」と問ひけれども、とかうの返事にも及ばず。具したる女に尋ねてぞ、去事有りとも知りてけり。
さるほどに、毎月贈られたりける百石百貫も、今はとどめられて、いまは仏御前のゆかりの者ぞ、始て楽しみ栄えける。京中の上下、
「祇王こそ入道殿のいとま賜はりて出でたるなれ。いざや、見参してあそばん」
とて、或は文をつかはす人もあり、或は使をたつる者も有り。祇王さればとて、今更人に見参して遊びたはぶれべきに有らず」
とて、文をとり入るる事もなし。まして使にあひしらふまでもなかりけり。これにつけても悲しくて、涙にのみぞ沈みける。
===第八捌節===
かくて今年も暮れぬ。あくる春のころ、入道相国、祇王がもとへ使者をたてて、
「いかに祇王。その後なにごとか有る。さては仏御前のあまりにつれづれげに見ゆるに、なにかくるしかるべき、参りて今様をもうたひ、舞なんどをも舞うて、仏なぐさめよ」
とぞ宣ひける。祇王御返事に及ばず、涙をおさへて臥しにけり。入道かさねて、使をたて、
「祇王、など返事をばせぬぞ。参るまじきか。参るまじくはそのやうを申せ。浄海がはからふむね有り」
とぞ宣ひける。
===第九玖節===
母のとぢ、これを聞きて、
「いかにや、祇王御前。ともかうも御返事を申せかし。かやうにしかられ参らせんよりは」
と言へば、祇王涙をおさへて申しけるは、
「参らんと思ふ道ならばこそ、やがて参るとも申さめ。参らざらんもの故に、何と御返事を申すべしともおぼえず。このたび『召さんに参らずは、はからふむね有り』と仰せらるるは、都の外へ出出さらるるか、さらずは、命を召さるるか、この二つには、よも過ぎじ。たとひ命を召さるるも惜しかるべき我身、嘆くべきに有らず。一度憂きものに思はれまゐらせ、二たびむかふべきに有らず」
とて、なほ返事を申さず。母とぢかさねて教訓しけるは、
「天が下に住まん者は、ともかうも入道殿の仰せをば背くまじき事に有るとぞ。男女の縁宿世、いまに始ぬ事ぞかし。千年万年と契れども、やがて離るる事も有り。あからさまとは思へども、ながらへは、つる仲も有り。世に定めなきは男女のならひなり。それに、我御前は、三年まで思はれまゐらせたれば、ありがたき御情にこそ有れ。このたび召さんに参らねばとて、命を召さるるまではよも有らじ。都のほかへぞ出だされんずらん。たとへ都を出ださるるとも、我御前たちは年若ければ、いかならん岩木のはざまにても、すごさん事やすかるべし。但、我身年老い、よはひおとろへて、都のほかへ出だされなば、ならはぬひなの住まひこそかねて思ふに悲しけれ。唯われを都のうちにて住みはてさせよ。それぞ今生、後生の孝養にて有らんずる」
と言へば、祇王、憂しと思ひし道なれど、親の命をそむかじと、泣く泣く出でたちける心のうちこそ無慚なれ。。涙のひまよりも、
''露の身の わかれし秋に きえはてで 又ことの葉に かかるつらさよ''
「ひとり参らんはあまりにもの憂し」とて、妹の義女をもあひ具しける。
===第十拾節===
そのほか白拍子二人、総じて四人、一つ車に乗り具して、西八条へぞ参りける。日ごろ召されける所へは入れられずして、遥かにさがりたる所に、座敷をしつらうて置かれたり。祇王、
「こはされば何事ぞや。我身にあやまる事はなけれども、捨てられ奉るだに有りし、いまさら座敷をさへさげらるる事の心憂さよ。いかにせん」
と思ふに、知らせじとする袖のしたよりも、あまりて涙ぞこぼれける。仏御前哀に思ひ、入道殿に申しけるは、
「さきに召されぬ所にてもさぶらはず、これへ召されさぶらへかし。さらずは、わらはにいとま賜はりて、出でて見参せん」
と申しけれども、入道「全てその儀有るまじ」と宣ふ間、力及ばで出でざりけり。
===第十一拾壹節===
入道出であひ対面し給ひて、
「いかに祇王、何事か有る。さては、仏御前があまりにつれづれげに見ゆるに、なにかくるしかるべき、今様一つうたへかし」
祇王、参る程ではともかくも仰せをば背くまじきものを」と思ひければ、落つる涙をおさへて、今様一つうたひける。月もかたぶき夜もふけて、心のおくを尋ぬれば、
''仏も昔は凡夫なり 我等も終には仏なり''
''いづれも仏性具せる身を へだつるのみこそ悲しけれ''
と、泣く泣く二返歌うたひたりければ、その座に並みゐ給へる一門の公卿、殿上人、諸大夫、侍に至るまで、皆感涙をぞ流されける。入道もおもしろげにて、
「時にとりては、神妙に申したり。この後は、召さずともつねに参りて、今様をもうたひ、舞などをも舞うて、仏をなぐさめよ」
とぞ宣ひける。祇王かへりごとに及ばず、涙をおさへて出でにけり。「親の命をそむかじとて、つらき道におもむき、ふたたび憂き目を見つるくちをしさよ」
===第十二拾貳節 (祇王出家)===
「生きてこの世に有るならば、又憂き目をも見んずらん。いまは唯身を投げんと思ふなり」と言ひければ、妹の祇女も、「姉の身を投げば、われもともに投げん」と言ふ。母とぢこれを聞き悲しみて、いかなるべしともおぼえず、泣く泣く又教訓しけるは、
「誠に我御前が恨むるも理なり。かやうの事有るべしとも知らずして、教訓して参らせつる事のくちをしさよ。但二人の娘共におくれなば、年老い、よはひ衰ひたる母、とどまりてもなにかせん。我もともに身を投げんなり。いまだ死期もきたらぬ親に、身を投げさせん事、五逆罪にや有らんずらん。この世はわづかに仮の宿りなり。恥ぢてもなにならず。今生でこそ有らめ、後生でだにも悪道へおもむかん事の悲しさよ」
と袖を顔に押しあてて、さめざめとかきくどきければ、祇王涙をおさへて、
「一旦恥を見つる事のくちをしさにこそ申すなれ。誠にさやうにさぶらはば、五逆罪は疑ひなし。さらば自害は思ひとどまりぬ。かくて都に有るならば、又憂き目をも見んずらん。いまは都のうちを出でん」
とて、祇王二十一にて尼になり、嵯峨の奥なる山里に、柴のいほりをひきむすび、念仏してぞゐたりける。妹の祇女も、
「姉の身を投げば、ともに投げんとだにちぎりしに、まして世をいとはんには、たれかはおとるべき」
とて、十九にて様をかへ、姉と一所にこもりゐて、後世をねがふぞ哀なる。母とぢこれを見て、
「若き娘共だにも様をかゆる世の中に、年老い、よはひおとろへて、白髪つけてもなにかせん」
とて、四十五にて髪を剃り、二人の娘もろともに一向専修に念仏して、偏に後世をねがふぞひける。
===第十三拾參節 (祇王出家)===
かくて春過ぎ夏たけて、秋の初風吹きぬれば、星合の空をながめつつ、天の戸わたるかぢの葉に思ふ事書くころなれや。夕日の影の西の山の端にかくるるを見ては、
「日の入り給ふ所は西方浄土にて有るなり。いつか我等もかしこに生まれて、物を思はですごさんずらん」
と、かかるにつけても、唯つきせぬものは涙なり。たそがれ時も過ぎければ、竹の編戸をとぢふさぎ、灯かすかにかきたてて、親子三人念仏してゐたる所に、竹の編戸をほとほとと打ちたたく者出できたり。其時尼ども肝をけし、
「あはれ、これはいふかひなき我等が、念仏してゐたるを妨げんとて、魔縁きたりてぞ有るらん。昼だにも人も訪ひこぬ山里の、柴の庵の内なれば、夜ふけて誰か尋ぬべき。わづかの竹の編戸なれば、開けずとも押し破らん事やすかるべし。なかなか唯あけて入れんと思ふなり。それに情をかけずして、命を失ふものならば、年ごろたのみ奉る弥陀の名号をとなへ奉るべし。声を尋ねてむかへ給ふなる聖衆の来迎にてましませば、などかは引摂なかるべき。あひかまへて念仏おこたり給ふな」
と、たがひに心をいましめて、竹の編戸をあけたれば、魔縁にてはなかりけり、仏御前ぞ出できたる。
===第十四拾肆節 (祇王出家)===
祇王、「あれはいかに、仏御前と見奉るは、夢かや、うつつかや」と言ひければ、仏御前、涙をおさへて、
「かやうの事申せば、なかなか事あたらしき事にてさぶらへども、申さずは又思ひ知らぬ身となりぬべければ、始よりして申すなり。
もとよりわらはは推参の者にて、出だされまゐらせさぶらひしを、祇王御前の申し様によりてこそ召し返されてさぶらひしに、女のかひなさは、我身を心にまかせずして、おしとどめられまゐらせし事、心うくこそさぶらひしか。我御前を出だされ給ひしを見るにつけても、『いつか我身の上とならん』と思ひしかば、うれしとはさらに思はず。障子に又『いづれか秋にあはではつべき』と書きおき給ひし筆のあと、『げにも』と思ひ知られてさぶらふぞや。
いつぞや又召されまゐらせて、今様うたひ給ひしにも、思ひ知られてこそさぶらひしか。このほど御ゆくへをいづくにとも知らざりつるに、かやうに様をかへて、一所にと承りて後は、あまりに羨ましくて、常は暇を申せしかども、入道殿さらに御用ひましまさず。つくづく物を案ずるに、娑婆の栄華は夢のうちの夢、楽しみ栄えても何かせん。
人身は受けがたく、仏教にはあひがたし。比度泥犁に沈みなば、多生曠劫を経るとも、浮かび難し。年の若きを頼むべきにも有らず。老少不定のさかひなり。出づる息の入るをも待つべからず。かげろふ、稲妻よりもなほはかなし。一旦の楽しみにほこりて、後生を知らざらん事の悲しさに、今朝まぎれ出でて、かくなりてこそ参りたれ」
とて、かづきたる衣をうちのけたるを見れば、尼になりて出で来たる。
===第十五拾伍節 (祇王出家)===
「かやうに様をかへて参りたれば、日ごろの科をゆるし給へ。『許さん』と仰せられば、もろともに念仏して、ひとつ蓮の身とならん。それもなほ心ゆかずは、これよりいづちへも迷ひゆき、いかならん苔のむしろ、松が根にもたふれ臥し、命の有らんかぎりは念仏して、往生の素懐をとげん」
と言ひて、袖を顔に押しあてて、さめざめとかきくどきければ、祇王、涙をおさへて申しけるは、
「誠に、それほどに我御前の思ひ給ひけるとは夢にも知らず、憂き世の中のさがなれば、身を憂しとこそ思ふべきに、ともすれば我御前を恨みて、往生をとげん事もかなふべしともおぼえず。今生も、後生も、なまじひにし損じたる心地して有りつるに、かやうに様をかへておはしたれば、日ごろのとがは露塵ほどものこらず。今は往生疑ひなし。このたび素懐をとげんこそ、なによりもつてうれしけれ。我等が尼になりしをこそ、世にありがたきやうに、人も言ひ、わが身も思ひしが、それは世を恨み、身を恨みてなりしかば、様をかゆるも理なり。我御前の出家に比ぶれば、事の数にも有らざりけり。我御前は嘆きもなし、恨みもなし。今年は僅かに十七にこそなる人の、かやうに
穢土をいとひ、浄土を願はんと思ひ入り給ふこそ、誠の大道心とはおぼえたれ。うれしかりける善知識かな。いざもろとも願はん」
とて、四人一所にこもりゐて、朝夕仏の前に花香をそなへ、余念もなくねがひければ、遅速こそ有りけれども、四人の尼ども皆往生の素懐をとげけるとぞ聞こえし。されば、後白河の法皇の長講堂の過去帳にも、
「祇王、祇女、仏、とぢが尊霊」
と四人一所に入れられけり。哀なりし事共なり。
==現代語訳==
===第一節===⏎
入道相国は天下を掌中に握ったので、世の非難を無視し、非常識な振る舞いばかりなさった。
たとえば、そのころ都で評判の白拍子の名手に祗王、祗女という姉妹がいた。とぢと言う白拍子の娘です。そして姉の祗王が入道相国の寵愛を受け、妹の祗女も並でない待遇を受けていた。母のとぢにも良い家を造って与え、毎月百石、百貫の銭を贈られたので、家中が富み栄え、裕福な暮らしをしていた。
そもそも、我が国に白拍子が始まったのは、昔、鳥羽院の時代に島の千歳、和歌の前、二人が舞いだしてからである。始めは水干に立烏帽子をかぶり、白鞘巻を腰に挿して舞ってるので、男舞と申していた。しかし、中ごろから、烏帽子、刀をつけずに、水干だけで用いた。そのことから、白拍子と名づけられた。
===第二節===
京中の白拍子たちは、祗王の幸運を羨む者や、妬ましく思う者がいた。羨む者たちは、
「本当に祗王御前は運が良いことだ。同じ遊女ならば誰も皆、彼女のようになりたいものだ。きっと名前に祗という文字が付いているので、縁起が良いのかも知れない。さあ我等もつけてみよう」
と言って、ある者は、祗一と付け、また、祗二と付け、あるいは祗福、祗徳などと言う者もあった。対して嫉む者は、
「どうして名や文字によるだろうか。幸運は前世の行いによるので、生まれつきなのだ」
と言って、名に祇の字を付けない者も多かった。
===第三節===
こうして三年という月日が流れたころに、また、都に評判の白拍子の名手が一人あらわれた。加賀国の者で名を仏と申して、年は十六ということであった。
「昔から多くの白拍子がいたが、このような舞は、まだ見たことがない」
と、京中の人々が、身分の上下に関係なく、もてはやすこと、普通ではない。仏御前が申すには、
「私は天下の評判になったけれども、今あれ程の隆盛を誇っている、平家の入道相国殿に、召されないのは、不本意なことよ。遊び者のならわしとして、何差支えなど無いでしょう。」
といって、ある時、西八条へ参上した。取次の者が参り、
「今評判の仏御前が来ておりますが」と申しあげると、入道は、
「何を言うか。そのような遊女は、人が召しに従って参るものだ。その上、祇王がいる所には、神と言おうが仏と言おうが、参ることは許されないぞ。さっさと退出しろ」
とおっしゃった。
===第四節===
仏御前は退出しようとしていたが、祗王が入道に、
「遊女の推参は、常のならわしです。その上、年もまだ若くございますが、何か思うことがあって来たのではないでしょうか。そんなに冷たく追い返しては可哀そうです。きっと恥ずかしく辛い気持ちになっていると思います。自分も同じ遊女として他人事とも思えませんので、たとえ舞を見なくても、また歌を聞かずとも、ここは一つ我慢して、お会いになってから帰させれば、有難いのですが」
と申すので、入道は、
「そうか、お前がそこまで言うのなら、引見してから帰そう」
と申して、使いを走らせました。仏御前は冷たくあしらわれ、車に乗って帰りかけていましたが、召されて、帰って参った。
===第五節===
入道が対面の場に出で、
「今日の引見は、ないつもりであったが、祗王が何を思ってかあまりにも勧めるので、このように引見した。会ったからにはやはり声でも聞かせてもらおうか。今様でもどうじゃ」
とおっしゃると、仏御前は、「解かりました」と、今様を一つ歌った。
''君に初めてお会いするときは 千年も命が延びるであろう、私、姫小松''
''御前の庭の池にある亀岡に 鶴が群れて遊んでいるようです''
仏は同じ節を三度繰り返して謡い終わりましたが、この今様を見聞きしていた人々は、その素晴らしさに驚きの声を上げました。入道もすばらしいと思われ、
「今様はなかなかのものじゃ。これなら舞もきっと上手であろう。一番舞ってくれ。鼓を用意しろ」
と、鼓を打たせて舞いを一番舞ったのでした。
===第六節===
仏御前は容姿が優れている上に、声も良く歌い方も上手なので、舞いをしくじることはありません。舞い終わると、入道は舞いをほめ、仏に気持ちを引かれていきました。仏御前が、
「これはどうしたことでしょうか、もともと私は押しかけ参上した者です。すでに帰ろうとしていた所を、祗王御前の願い出によって、呼び返されたものです。はやくお暇を頂き帰りたく思います」
と、申しますと、入道相国は、「それはならぬ。祗王がここに居るのでそのようなことを言うのか。それならば祗王を追い出そう」
と、おっしゃりますと、仏御前は、
「これはまた、何ということでしょう、祗王御前と共に召し置かれるだけでも、恥ずかしいことですのに、祗王御前を召し放って、私だけを召されたりしますと、祗王御前のお気持ちはどれほど恥ずかしく、辛いことで御座いましょうか。もし後々まで私のことを覚えていただけたなら、その時またお呼びください。また参りましょう、しかし今日はこれでお暇くださいますよう」
と申しました。入道、
「よしそれなら、祗王、暇を出す。ここを退出せよ」
と、三度も使いの者にせかれました。
===第七節===
祗王は以前より何時かこのようなことがあろうと、思っていたことですが、さすがに昨日今日なんては思っても居ませんでした。入道相国はしつこく言いますので、部屋を掃除し、塵など拾って片付けてから、出て行こうと決心しました。
たまたま出会った人と一本の木の下に居たり、同じ川の水を飲むだけの仲でも、別れというものは悲しいのに、三年も住み慣れた所ですので、名残も惜しく悲しくて泣いても仕方が無いとは、分かっているのですが、涙が止まりません。何時までもぐずぐず出来ませんので、祗王は思い切って出て行こうとしましたが、私が居なくなった跡の忘れ形見になればと、障子に一首の歌を書き付けたのです。
''萌え出るのも 枯れるのも 同じ野辺の草で いずれは秋に あって枯れてしまうだろう''
さて祗王は車に乗って宿所に帰ってきたのですが、部屋に倒れこみただただ泣くばかりでした。母親や妹がこれを見て、どうしたのかと尋ねても祗王は何も答えられません。そばの供の女に尋ね、初めていきさつを知りました。
その内毎月の援助の百石、百貫も止められ、今度は仏御前に所縁のある人々が始めて幸せになりました。京中の人々はこの噂を聞いて、
「本当だ、祗王は西八条殿より暇を出されたそうだ。それなら一度参って遊ぼう」
と、手紙を出したり、使者をよこしたりする者も居ましたが、祗王は今更また人に会って遊ぶなんてことも出来ませんから、手紙を読むこともせず、ましてや使いの者に会うことなどしませんでした。祗王はただただ悲しくて泣き暮らしていました。
===第八節===
こうして今年も暮れました。翌年春になりますと、入道相国は祗王の所へ使者を遣わし、
「どうしているか、祗王よ。その後何か変わったことはないか。仏御前があまりにも寂しそうにしているので、こちらに参って今様を詠ったり、舞などを舞って仏を慰めてくれ」
と、言わせました。祗王は何ら返事をすることも無く、涙を抑えて臥せてしまいました。入道は再び、
「なぜ祗王は返事をよこさないのだ。来るのか来ないのかはっきりしろ。この浄海にも考えるところがことがある」
と、おっしゃってきました。
===第九節===
母とぢはこれを聞いて大変悲しみ、泣く泣く祗王にさとしました。
「なぜ祗王は返事もせずに、このようにお叱りを受けているのか」
それに対して祗王は、
「参ろうと思えばすぐに返事も書けますが、参る気持ちが無いので返事のしようが無いのです。この度お言葉にありましたように、こちらにも考えがあるということは、きっと都を追い出されるか、そうでなければ、命を取られるかのどちらかでしょう。 たとえ都を追い出されても嘆くほどのことも無いし、また命を召されても惜しいわが身ではありません。しかし一度嫌われたのに、またお会いすることなんて出来ません」
と、涙を抑えて申し、なおも返事を書こうとはしませんので、とぢは泣きながら話しました。
「この世に住もうと思えば、どんなことがあっても入道殿の言われることに逆らうことは出来ません」
とぢはなおも続け、
「その上男と女の縁や宿命は今に始まったことではないことは、貴女も知っているでしょう。千年万年と契った仲でもその内別れる者も居れば、ちょっとのお付き合いと思っていても、生涯添いとげることもある。この世で男と女の先の事なんて、誰にも分かりはしないものです。まして貴女はこの三年の間、あの入道殿のご寵愛を受けたということは、ありがたいことです。この度のお呼びに参らないからといって、命を取られるなんて事は、あり得ません。きっと都の外へ追い出される位でしょう。たとえ都を離れても貴女はまだまだ若いので、どのような所でも暮らすことは出来ます。しかし私は年老い、体も弱ってきていますので、慣れない田舎暮らしは考えるだけでも悲しいことです。せめてこの母を都に住み続けさせて下さい。それが現世、来世の親孝行ではないでしょうか」
と、言いますと、祗王は行くまいと心に決めていたのですが、母の命令に背くことも出来ず、泣く泣く出掛けたのです。
彼女の辛い気持ちは本当に無残なものです。祗王一人で参るのはあまりにも辛いことなので、妹の祗女と、白拍子二人総勢四人、一つの車に乗って西八条に向ったのでした。
===第十節===
呼ばれた時のいつもの席には着けず、遥か末席に座らされたのです。祗王は、
「これはどうしたことでしょう。自分には何も落ち度が無く、訳も無く捨てられた上、こんな末席に座らされるなんて本当に悔しい。 どうすれば良いのでしょうか」
と、思えば悲しくて、人には見つからないようにとは思ったのですが、袖の隙間から涙があふれました。仏御前は祗王の姿を見て、あまりにも可哀相に思いましたので、入道に、
「どうしたことでしょう。あそこに居られるのは祗王様では御座いませんか。いつもと違う席に居られるではありませんか。こちらにお呼びしましょう。そうでなければ私にお暇を下さい。席をはずしましょう」
と、申しましたが、入道はそれはならぬと言いますので、 仕方なくそこに居ました。やがて入道は
===第十一節===
祗王に対面し、
「どうじゃ祗王、その後何か変わったことはないか。仏御前があまりにも寂しそうに見えるので、今様でも詠ったり、舞などを舞って仏を慰めてくれぬか」
と、おっしゃいました。祗王もこうして参った以上、入道の言葉に逆らうわけも行かず、涙を抑えて今様を一曲詠いました。
''仏も昔は凡人であった 我等もついには仏になる''
''いずれも仏性を備えている身でありながら 隔てられていることは悲しい''
泣く泣く二回詠いますとその座に居る平家一門の公卿殿上人、諸太夫から侍に至るまで、皆感激して涙が流れたのです。入道もさすがにそうであろうと思い、
「即興にしては素晴らしいぞ。舞いも見たいが今日は所用が出来て見ることが出来ない。しかしこれからは、こちらが呼ばなくても参って、今様を詠ったり舞などを舞って、仏を楽しませてくれ」
と、言われました。
祗王は何らの返事もせず涙をこらえて退出したのです。祗王は、「行かないと心に決めていましたが、母の命令に背くわけにも行かず、辛いとは思いながら参ったのですが、あのような辱めを受けるのはなんとも悔しいことです。」
===第十二節===
「こうして生きていると、また同じように辛い目に逢うでしょう。今はもう死にたいと思います」
と、言いますと妹の祗女はこれを聞いて、「姉上が身投げするなら、私も一緒に」と、言います。
これを聞いていたとぢは、悲しくて仕方ありませんが泣きながら言い聞かせるのは、
「そのようなことがあるとは知らずに、言い聞かせ無理やり入道のもとに行かせたのは、私の間違いでした。本当に貴女が悲しみ嘆くのも無理無いと思います。そうは言っても貴女が身を投げたら、妹の祗女も身を投げると言っている。若い娘を先立たせて年老いた母が、生き永らえても仕方が無いので、そのときはこの母も一緒に身投げしようぞ。しかしながらまだ死期が来ていない母に身投げをさせることは、五逆罪にあたるぞよ。この世は所詮仮の住まいなので、どんなに恥をかこうとも、たいしたことはありませんが、ただこの世での永くて暗い生活を思うといやになります。この世でもこれなのに、来世に悪道に落ちていく事はなんとも悲しいことです」
と、さめざめと泣きながらくどくど言います。祗王はこれを聞いて涙を流しなら、
「なるほどそう言うことならば、五逆の罪に問われることは間違いが無いでしょう。一旦は恥をかくことの辛さから逃げたさに、身を投げてしまおうと言いました。しかしこうなれば、自害は思いとどまりますが、このまま都に住んでおればいつかまた、いやなことが起こると思います。そこでこの際都を出て行こうと思います」
と、祗王は二十一歳にして尼になり、嵯峨の奥里に柴の庵を結んで念仏三昧の日を送ったのです。
妹の祗女はこれを聞いて、
「姉上が身を投げるなら、私も共にと思っていましたが、私とてこの世を疎ましく思う気持ちは誰にも負けません」
と、十九歳にして出家し姉と一緒に庵に篭り、ただ一筋に後生を願い続けたのです。母のとぢも、
「若い娘たちが出家してしまったこの世で、年老いて体の弱った母が、白髪を守っている事が何になるのか」
と、言って四十五歳にして髪を剃り、二人の娘たちと共に、ただひたすらに念仏し、後生を願い修行されたことは、また哀れなことです。
===第十三節===
このようにして春が過ぎ夏もたけなわになりました。やがて秋を告げる風が吹きますと、七夕の空を眺めながら、天の川を渡る楫の葉に溜まる水を使い、墨を磨り願い事を書く頃になりました。夕日の影が西山の端に隠れようとするのを見ても、
「あの下には西方浄土があるのでしょうか。いつか私たちもそこに生まれ変わり、何も考えずに過ごすことが出来ますように」
と願いながらも、つい今までのいやなことを思い続けて、涙が尽きることはありません。たそがれ時も過ぎ日も暮れたので、竹の網戸を閉じて、明かりも控えめにして、親子三人が念仏をあげているところに、網戸をほとほととたたく者が居ます。三人の尼たちは恐ろしくて、
「あれまあ、これは私らみたいな者が、念仏しているのを邪魔しようと魔物が来たのではないかしら。昼でも誰も訪ねてこない山里の、粗末な庵に夜がふけてから、一体誰が訪ねてくるというのでしょう。竹の網戸くらいは開けることをせずとも、押し破って入ってくることは簡単でしょう。むしろ今は網戸を開けて入れようと思います。そうせずに命を失うなんてことがあれば、いつも頼みにしている弥陀の本願を信じて、もっともっと熱心に念仏を唱えましょう。念仏の声を訪ねて来られた菩薩様のご来迎であれば、どうして引導を渡されることがあろうか。決して念仏をやめるではないぞ」
と、お互いに心を引き締めて、手に手をとって竹の網戸を開けてみますと、魔物ではなく、仏御前が居られたのでした。
===第十四節===
祗王が、「一体これはどうしたことでしょう、仏御前ではありませんか。夢ではないでしょうね」と、言いますと仏御前は涙を抑えて、
「このようなことをお話するなんて、今更わざとらしいと思いますが、お話しをしなければ何も分かってないとも思われますので、事の次第を始めよりありのままに、お話させてください。
もともと私は押しかけていった者でございまして、すでに追い返されたところを貴女の取り計らいによって、呼び返されたのです。女の身であれば思うようにならず、貴女を追い出して私が残る事になりました。今となれば恥ずかしくまたみっともなく、申し訳なく思っています。
貴女様が出て行かれるのを見たときも、何時か自分もあのような目に逢うのだろうと思いますと、とても嬉しいなんて事は感じませんでした。また障子に『いづれかあきにあはではつべき』と書き置かれた筆の跡を見たとき、成るほどと思いました。
またその後貴女様が召されて、今様をお詠いになられた時も、わが身の行く末を身にしみて分かったのです。また貴女様の行く先も分からず居りましたが、この度このようにご出家され、念仏三昧のお暮らしをしておられると聞き、あまりにうらやましくて、いつも入道様に暇を頂きたくお願いをしていましたが、許されませんでした。
よくよく考えてみますと、この世の栄華なんてものは夢の中の夢であり、どれほど楽しくてもそれが一体何かと思います。人間の肉体は授かることが難しく、仏の教えにはあうことが難しいと言います。この度地獄に落ちましたら、どれほどの時間をかけたとしても、浮かび上がってくることは難しいと思います。老少不定というように年老いたものが先に死ぬわけでもなく、年が若いということも何もなりません。はいた息が再び戻ってくることが無いように、陽炎や稲妻よりもっとはかなく、一時の栄華におぼれて、死んだ後のことを知らないことが悲しくて、今朝このような姿になって、舘を紛れ出てきました」
と、言ってかぶっていた着物を取りますと、すでに尼の姿になっていました。
===第十五節===
「このように髪を剃って参った上は、俗世での罪はどうかお許しください。もし許すとおっしゃって頂けましたら、ご一緒に念仏して極楽浄土にて同じ蓮台に座りたく思います。それでも駄目だとおっしゃるのでしたら、いまから何処かに迷い行き、どこかの苔のむしろか松の根元にでも倒れ臥せって、命のある限り念仏し往生を遂げたいと思います」
と袖を顔に押し当て、さめざめと泣きながら言いますので、祗王も涙をこらえながら、
「貴女様がそこまで思っておられるとは、夢にも知りませんでした。浮世のならわしだと思いながらも、わが身の辛さにともすれば、貴女のことを恨んだり、この世も来世も中途半端にやりそこなった気持ちで居りましたが、このようにご出家されておられますので、今までの恨みやその他のことは皆なくなりました。いまはもう極楽往生は間違いありません。
この度日頃の願いが遂げられるとは、何よりも嬉しく思います。私が尼になりましたことでも、世間では滅多に無いことのように言いますし、自分でもそう思って居りました。その訳は世の中を恨み身を嘆いていましたので、出家ということを選んだのです。
貴女様は特に恨みや嘆きもなく、今年わずか十七歳の若さで、それほどこの穢土ともいえる世を嫌い、浄土を願う思いが強いことは、本当の求道者と思います。嬉しくなるほどの善智識かも知れません。
さあご一緒にお願いいたしましょう」
と、四人一緒に庵に篭り、朝夕仏前に向い花や香をお供えし、長年念仏を唱えていました。遅い速いはありますが皆極楽往生の願いを、遂げられたと言われております。
そういう訳であの白河法皇が建立された長講堂の過去帳にも、祗王、祗女、仏、とぢの尊霊と、四人一緒に名前が書き加えられています。まことにありがたいことです。
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|